「教育」総点検 [イハトビラキ]
世界基準にも合わせられるしちょうど良いと。
でもね…どーせ変えるなら、時期の問題だけでなく、
公教育の在り方自体にメスを入れた議論が欲しい。
日本では633制が当然とされているが、
ますます進む少子化によって廃校になる学校も増えていく。
テレワークならぬテレ授業も推進されていく。
学校の長期休業で、自主的に勉強を進めていく子供も少なからずいる。
結果の平等を目的とした今の学校制度自体があらゆる子供の教育に
対応できないという事実が露呈しただけではないのか?
家で学習することが当たり前になったほうが日本の教育水準は
全体としては飛躍的に向上する。
一人の天才は10万人を養えるという見方もあって、
今の教育制度では、日本から突き抜けた天才は出てきにくくなっている。
官僚が日本と言う国家の根源的な権力を有している源こそ…
東大を頂点とした今の教育制度ではないのか?
132 名前:堺のおっさん2020/04/30 (Thu) 08:37:06
学校の9月開始論がうるさい。
ところで、武漢ウイルスが収束して、
10年後にまた同じような事態になったら…
また、4月開始に戻すのかね。
事の本質がずれまくってる。
一斉に教育を施さなければならないという
かつて、国民皆教育が均一な労働力の確保と
エリート育成のために発足したところから
総点検しなければ結論は出ない。
飯山氏は「学校に行くな!」と独自の教育論を展開されていたな。
ただ、現行制度では特に中3、髙3が影響を受けるのも事実。
入試の時期に絡んで、ある意味部分的でもある。
柔軟な制度にすることでクリアできる。
自学自習を評価し、サポートする制度をどう組み込むか。
東大も変わらなければならない。
教育産業も変わらなければならない。
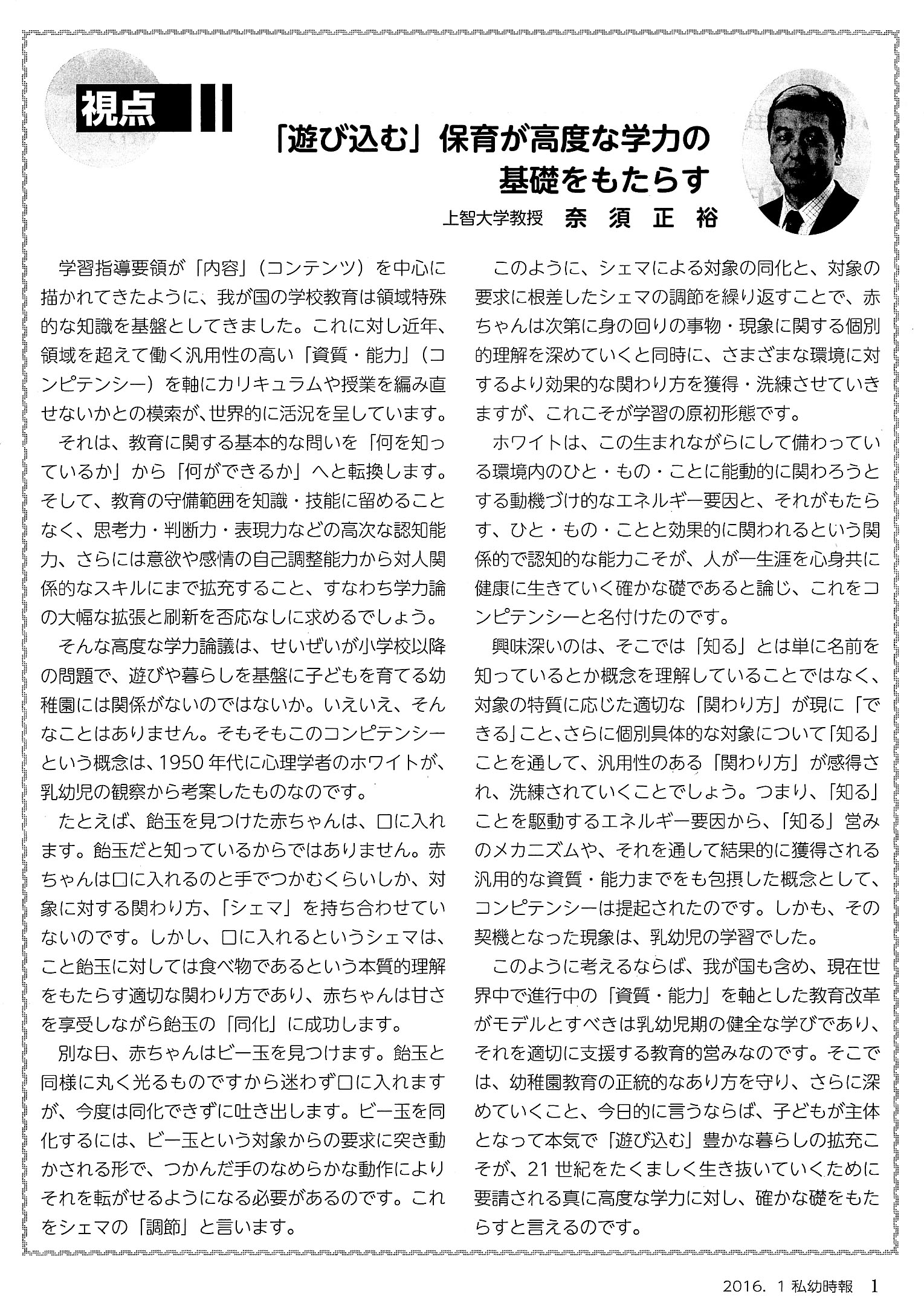
《 学習指導要領が「内容」(コンテンツ)を中心に描かれてきたように、我が国の学校教育は領域特殊的な知識を基盤としてきました。これに対し近年、領域を超えて働く汎用性の高い「資質・能力」(コンピテンシー)を軸にカリキュラムや授業を編み直せないかとの模索が、世界的に活況を呈しています。/それは、教育に関する基本的な問いを「何を知っているか」から「何ができるか」へと転換します。/そして、教育の守備範囲を知識・技能に留めることな<、思考力・判断力・表現力などの高次な認知能力、さらには意欲や感情の自己調整能力から対人関係的なスキルにまで拡充すること、すなわち学力論の大幅な拡張と刷新を否応なしに求めるでしょう。》
《教育に関する基本的な問いを「何を知っているか」から「何ができるか」へと転換します。》この部分、私にはほんとうに感慨があるのです。やっぱりこう言われる時代が来たと思い、人知れず悦に入ったのです。
学生の時ですからもう50年近くになります。教職単位のためのまったく面白くもない「教育原理」の講義、「日本の教育は主知主義を原理とする」と最初に言われたのです。そこでデカルトの「われ思う、われあり」も言われたと思います。私にはそのことに異和感をおぼえ、わだかまることになります。そのうち大学紛争の嵐があって、多少は揉まれてもみたり、渦から抜け出て斜に構えてもみたり、そんなこんな中でメルロー・ポンティに出合って、ようやく「あたりまえ」の大切さが少しずつわかるようになって、本気でメルロー・ポンティを読むようになって《意識とは原初的には〈われ惟うje pense que〉ではなく、〈われ能うje peux〉である。》("Phénoménologie de la perception" p.160)の言葉を見つけたのでした。私には、「われ思う、ゆえにわれあり」に対する真っ向からの挑戦に思えて快哉・・・だったかどうだったか、じわーっとその意義がわかるようになったのかもしれないのであまりなことは言えませんが、とにかく以来、「われなし能う、ゆえにわれあり」の言葉が「われ思う、ゆえにわれあり」を駆逐する時がいつか必ず来るにちがいない、とずーっと思いつづけて半世紀近く、そしてようやく昨日の出合いだったのでした。
* * * * *
つづけて、《十数年前に書いた文章です。》として、副島板への異和について書いた時の文章をコピペしています。https://oshosina.blog.ss-blog.jp/2016-01-07 そもそも「「損得の視点」を超えるもの 」と題して書いたものでした。https://oshosina.blog.ss-blog.jp/2006-06-03 「コロナ騒ぎ」収束後の世界とは、まさに「損得の視点」を超えた世界ではないかと思えます。
【追記 2.5.6 6:10】
奈須先生のいい文章を見つけた。
◎「深い学び」の捉え方 https://shop.gyosei.jp/library/archives/cat01/0000000775
《自分との関係において意味の発生しない機械的学習は、いかにも浅い学びであろう。つまり、学習の浅い・深いとは、学習者における意味の発生の有無なり、そのまさに深さの度合いであり、鍵を握るのは既有知識との関連付けの有無なり深さの程度なのである。》《およそ小学校で教える内容であれば、それに関して子供たちが何も知らないということはありえない。にもかかわらず、従来の授業でそれを十分に活かしてこなかったのは、これらの知識が時に不正確であり、断片的だからだろう。しかし、不正確で断片的だからこそ、そこに切実な問いが生じるのであり、それを解き明かしていく中で、知識はどんどん正確になっていき、統合的な概念へと深みを増していく。/ 授業とは何も知らない子供に何事かを教え込む営みではなく、すでにいい線まで知っている子供たちに、その知識の整理・統合・洗練の機会を与え、素朴で断片的な知識を科学的で概念的な理解へと深めていく営みなのである。》
「できる=身につく」です。教育、学習の目的を明確にそこに据えねばなりません。知識の多さ自体を誇る時代ではない。その知識が自分にとってどう意味づけられているか、そういう知識の学びでなければ意味がない。




コメント 0