「心」と「情(こころ)」(若松英輔) [若松英輔]
情とは何か〜ピカート『沈黙の世界』 若松英輔
言葉のちから
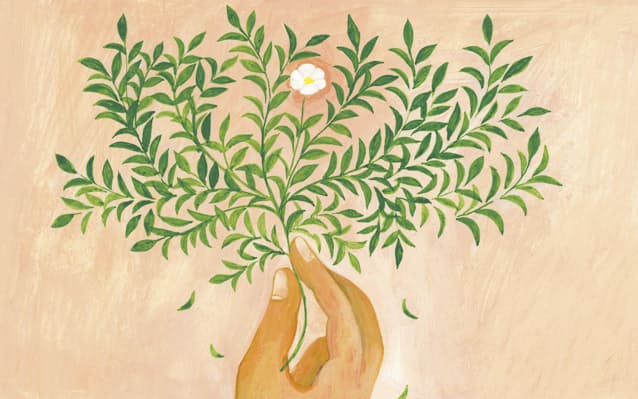
本格的に文章を書き始めるようになってからずっと、どこかで「情(こころ)」とは何かを考えている。心情という言葉もあるが、「心」と「情」のあいだには、これらを同じものだといって終わりにできない何かがあるように感じられてならない。
「情」が終わりのない問いになったのは、その表現に苦しんだからだった。書くときも、話すときも、「心」の世界であれば、言葉を尽くせばどうにかなる。「情」は違う。巧みに言葉を用いたとしてもまったく浮かび上がってこない。
振り返ってみると、文章を書くようになった動機も、人前で話せば脇の下にぐっしょり汗をかくような性格であるのに、講演や講座を生業(なりわい)にしていこうと決めたのも、抗いがたい情の躍動のためだった。情の世界で培われた経験の蓄積が、強靱(きょうじん)な勢いで自分を突き動かすのである。
情(じょう)が深い、情が薄(うす)いというとき、私たちは「情」という文字をほとんどその人そのものの代名詞として用いている。「心」をめぐっては、心が広い、心が狭い、などという。どちらも私たちの現実だ。人は常に二つの「こころ」を同時に生きているらしい。「心」が、その人の内面の状態を表わすとしたら「情」は、その人自身のありようを意味するのではないだろうか。
騒がしい心に煩(わずら)わされていても、少し静かな時間があれば、落ち着きを取り戻せる。しかし、情を整えるのはそう簡単ではない。一朝一夕にはいかず、持続的な鍛錬が求められる。気分を整えるのと人格を深化させるのは、まったく異質な営みなのである。
先にもふれたが、情の世界を描こうとするとき、言葉に技巧を凝らしてもうまくいかない。情が顕現するのは文章の内容であるよりは文体においてであり、発言においてであるよりも、その人が醸し出す雰囲気や間(ま)においてなのである。
落語の世界に通じた人と話しているとき、師匠から話法を学ぶのはさほど難しくない。習得するために人生を賭さなくてはならないのは間のほうだ、ということになった。その話を聞きながら、文学だけでなく、仕事の現場でも同じだと思った。
もったいぶった態度が作る間は人を不安にする。だが、自ずと生まれてきた間において人は、語られざる真実と称したくなる何かを見出す。
言葉が終わったところに間が生まれる。それが日常生活の実感かもしれないが、そうした見解に異を唱える人もいる。巨(おお)きな間があるからこそ、人は言葉を発することができる、というのである。マックス・ピカートというスイスの哲学者もそうした人物のひとりだ。代表作の一つ『沈黙の世界』には次のような一節がある。
「沈黙は、そのなかに住むもろもろの事物に、沈黙の有する存在の力を頒(わか)ちあたえる」(佐野利勝訳)
彼のいう「沈黙」は、巨大な間、深甚な間に置き換えてよい。「沈黙の有する存在の力」という表現は少し難解に感じられるかもしれない。むずかしく考える必要はない。生ける間によってつながるとき、私たちは、信頼という出会いの果実を得ている。この日常的な事実を想い出せば十分である。
近年、教育だけでなくビジネスの世界でも、知性偏重が反省され、感性を磨くことが奨励されている。もっと心を働かせなくてはならないという意図は分からないではない。確かに現代は、合理と倫理だけでは読み解けない時代だ。だが問題は心を働かせていないことにあるのではなく、あまりに心を頼みにし、情というもう一つの「こころ」を見過ごしているところにあるのではないだろうか。
仕事の現場に「情」は禁物である。私情や感情をもちこんではならない。どんな職場でも飛びかう常套句である。しかし世にいう私情や感情は、これまで見てきた「情」とはほとんど関係がない。むしろ、一時的な「心」の高ぶりであり、あえて情という言葉と結びつけるなら激情と呼ぶべきものである。
激情は誤った場所に導くだけでなく、長く築き上げたものを一瞬にして破壊する。激情を退け、情を取り戻す。その第一歩が「心」と「情」のあいだに小さな、しかし確かな質的な差異を認識することなのである。
心は、勢いを得ると、どこまでも拡(ひろ)がろうとする。「情(こころ)」は、どこまでも深まろうとする。探しているものは、どこか遠くにではなく、今いる場所を少し掘ったところにある。そう語る賢者は、歴史上にもけっして少なくないのである。
(批評家)




1919年(大正8年)、大本の出口王仁三郎の教義に失望して脱退した。静岡県に移住し、王仁三郎の師の長沢雄楯(本田親徳の弟子)から本田親徳の霊学を学び、これをもとに大本批判の書『乾坤一擲』『事実第一』を著した。また、佐曽利清(さそり あかし)など長沢雄楯以外の本田親徳の弟子にも接触し10月に『鎮魂帰神の原理及び応用』を著した。これは本田親徳の考案した鎮魂法の初公開の書であった(現在、天行居で行われている音霊法は佐曽利の直伝であったとい
by お名前(必須) (2023-05-28 21:55)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8B%E6%B8%85%E6%AD%93%E7%9C%9F
by お名前(必須) (2023-05-28 21:58)
かなり理屈っぽく感じました
by お名前(必須) (2023-05-28 22:00)