小田仁二郎の現在的意義を探る(市民大学講座)(下) [小田仁二郎]
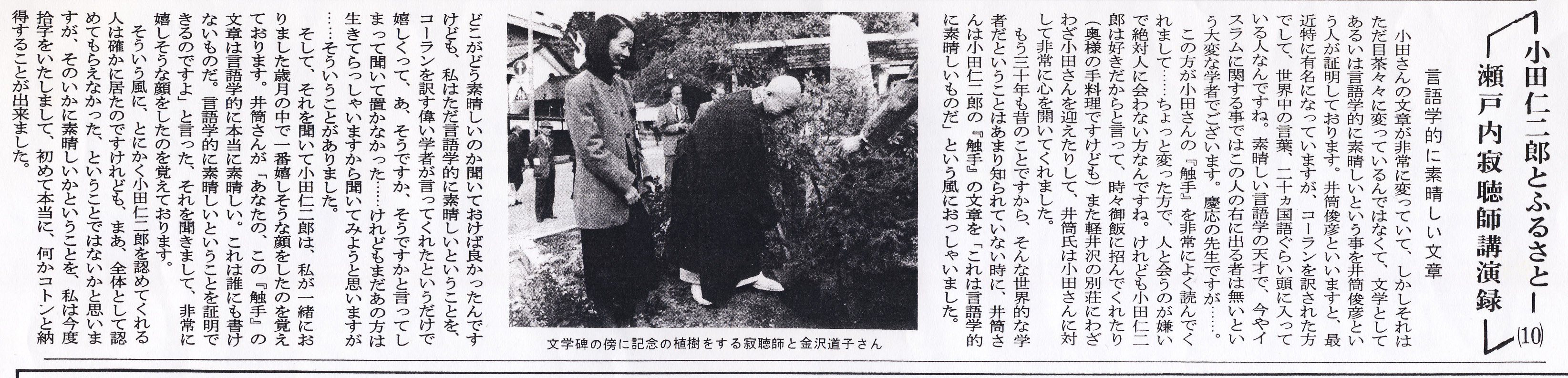
○種村季弘の「にせあぽりや・触手」論(種村季弘文芸評論集『器怪の祝祭日』昭和59年)
(種村季弘:”世界に誇るべき「知の無限迷宮」の怪人”)
《アポリアといえば、行手に通うべき道なきこと、すなわち八方塞がりであり、転じて難問の意である。・・・これは出口のない独房に閉じ込められた自殺志願者の告白的回想である。主人公の素姓は、明治のどさくさに成り上がったらしい元博打打ちの三代目、父の代の医業を食いつぶした極道青年である。「触手」もほぼ同じ主題を、独房の狂人の視点から叙べた小説であるから、右の二つの作品は、明治大正昭和三代に亘る近代日本の栄枯盛衰を旧家の宿命に仮託して描く伝統的な自然主義的私小説に踵(きびす)を接しながら成立していると言っていい。
三半世紀ぶりの再読と書いたが、・・・連用どめの反復からなる晦渋な文体に辟易しながら読んだ記憶がある。極度に抽象的な観念小説という読後感が残り、へとへとになった。
・・・昭和23年当時の高校生の小説読者に難解と思われたのは、むしろ出口という出口をしらみつぶしに塞いでは自ら作り上げた八方塞がりを手探りにひとつひとつ確かめている、不可解な作業だったのだろう。どこにも抜け道のない、すなわちアポリアと化した言語空間。・・・昭和初年代文学の最終的帰結であり、戦時下の閉塞状況にとことんまで馴染んでいる(昭和23年ながら制作年代は10年代末ではないか)。・・・一人後進の小田仁二郎のみが、より後続の戦後作家のはなばなしい出発を見送りながら、怖ろしく長い猶予の時を持久していた。》
《主題からいえば酸鼻をきわねる血の頽廃を書いた自然主義小説にそっくりでありながら、現実と見合う力のない未生児の追憶として書かれているので、すべてがもはやない世界として現前しており、あるいはこの未生児は死産児として流されることになるのだから、これから先もありえない世界として現前している。書かれた内容を裏切って、作品の読後感が一種あえかな王朝風のみやびを喚起するのはそのためだ。あえていうなら『桜の園』の透明な終末感、いや、見渡せば花も紅葉もない藤原定家の匂いたつ虚無の香りが、血と精液にまみれたむごたらしい宴の後に立ちこめる。死母の巨大な汚洞は、それが生み出した無惨な人間と現実を呑み込み破壊しはするが、同時に言語として虹のような七彩の夢を紡ぎ出すのである。・・・生の官能をことごとく鏖殺(みなごろし)しおえた後に来る言語の官能の響きである。しばしば誤解されてきたように、小田仁二郎は肉体派文学の旗手ではなかった。
すでにして母胎は生み出すべき何物も孕むことのない空の器である。昭和初年代文学の帰結として、小田仁二郎は、このもはや何もない、何ひとつ起り得ない場所に逢着した。そこから先には何もないどん詰り、袋小路である。それはしかし生のものの生成に関する限りであって、言語の生成についてはその限りではない。かえってすべてのものが死に絶えたからこそ何かを言う、というのが悲歌の、鎮魂歌のあり方である。だからこそアポリアではなくて「にせあぽりあ」であった。
この空の器からはあらゆるものが言語として取り出せる。そして太宰治ほど終末の意識をナルシスティックな自家消費に使い尽したのではない小田仁二郎の場合には、空にするまでが自分の作業であっても、空の器から言葉を取り出すのがかならずしも自分ではなくてもよかった。自分であってもよかったが、戦後の作家は職業作家として空から花を咲かせることにそれほど躍起ではなかったようだ。その代りに同人雑誌の教育家として他人に花の栽培を譲ろうとしたのかもしれないが、そこから巣立った某女流の仕事に通じていない私には、これを何とも言うことができない。
ただ、ある双生児的な並行現象がかなりかけ離れていると見えるところで起った。『触手』の後四半世紀を経て書かれた三島由紀夫の『天人五衰』である。この作品にも三保の死んだ暗い海の寄せ返す終末意識のうねりがくり返し起伏しながら、結末において記憶も何もない小さな庭に一切が収斂して行く。この何もない庭もまた、奇術師の空っぽのシルクハットのように、そこから何でも取り出すことのできる空の器である。あるいはそのはずである。》
①戦時下の閉塞状況の中の極限
②”見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋秋の夕暮”藤原定家
③「肉体派」ではない。《生の官能をことごとく鏖殺しおえた後に来る言語の官能の響き》
④「現実の生」の極みから見えてくる無限の「言語世界」
⑤《空にするまでが自分の作業であっても、空の器から言葉を取り出すのがかならずしも自分ではなくてもよかった。》→瀬戸内寂聴
⑥三島由紀夫の『天人五衰』は双生児
-
福田恆存による『触手』の巻末解説
(福田恆存:「人間は生産を通じてでなければ付合えない。消費は人を孤独に陥れる」。小林よしのり「福田恆存のこの言葉を噛みしめよ」)
《優れた芸術さ需品は注釈や解説を必要としないというのは半面の心理にすぎない。とはいえ。解説なくしては誤解や拒絶にあうというのも、やはり作家の不幸であろう。小田仁二郎はそういう不幸をまぬがれぬ作家のひとりとおもわれる。かれは現代の日本において、その文学的水準に比して、少し新しすぎる小説家なのである。さらに誤解の種とならなければさいわいだが、「にせあぽりや」や「触手」はヨーロッパ文学の今日の水準に達している作品であり、その土地に移し植えても依然として新しさを失わぬものであるにそういない。きょうの日までかれが、先輩やジャーナリズムのあいだにあって、理解されずに埋もれていたのは、また当然といえよう。》
《かれは、現実のあらゆる単位のうちにひとびとの仮想している特異性や個性を、一切否定してかえりみぬ。そんなものはかれにとってつまらぬものであり、どうでもいいものでしかない。いや、かれは個性というものをはじめから信じていないのである。そのようなものを軽信するするセンチメンタリズムを、かれは頭から軽蔑している。かれの眼から見れば、ひとびとの性格とみずからみなしているところのものは、すべてとらわれた固定観念やコンプレックスの、乱雑きわまる、偶然の集合体にすぎないのだ。ひとびとはこのでたらめの寄せ集めを性格と称し、これを聖化して自我と呼んでいる。》
《「触手」はただ受容するだけである。死を強いられても反発しはしない。ーー触手はただあらんかぎりの力をめざまして死を感覚しようとするだけである。死の感度表を完璧に作製することこそ、もっとも生のリアリティを把握したことになる。ーーそう考えてみたうえでの肉体の、あるいは性欲の秘密に近づこうというのが、作者の目的なのだ。》
《小田仁二郎の作品はあくまで知性の文学であって、一見そうみえるように感覚の世界にあるものではない。
したがって。その精神はあくまで実証主義的である。経験主義であるといってもいい。自分の眼しか信じない。いや、眼はすでにあまりに精神的であるがゆえに、規制の見方に欺かれやすい。もっとも原初的な、無垢の感覚、それは触覚である。が、それすらあてにならぬ。近代人の感覚は既成概念や意識の歪曲にあって、すっかり摩滅し、死にはてている。小田仁二郎はいま、なんら既成概念も先入観もなくはじめてこの世界にはいってきて、感覚以外のなにものも隔てずにじかに現実に接触する嬰児の、あの原初的な一人称を回復せんとくわだてるのだ。
「にせあぽりや」では、その技法はいまだ 一人称と三人称との交錯に終始している。が、「触手」においては完全な一人称小説がーーおそらく日本ではじめて ーーうちたてられたといえるであろう。・・・作者は、三人称の、すなわち他人の、あるいは他人に教えられた、レディ・メイドの見方を徹底的に排除しているのだ。いわゆる私小説にとって好個の材料たる家族のもめごとや、父の放蕩や、母の死や、その他あらゆる家庭的な日常世界は、もめごとをもめごとと教えこまれていない子供の眼には、それこそ「にせあぽりや」や「触手」における状景としかうつらぬであろう。それが真のリアリティというものなのだ。・・・他人の存在を意識することによって、ひとははじめて自己を確認する。・・・が、じつは、三人称をうちに含まぬ一人称は存在する。ひとびとがこの場合一人称というのはたんなる自我意識にすぎぬのだ。・・・(「触手」の作者は)一人称をこの自我意識のそとに設定しようともくろんだのである。・・・かれが新しいのは、・・・能動性を欠いた性格の弱さを究極にまで押しつめ、そこで負を正にかえた強さであり、新しさである。そとがわからいえば、自意識の充満した近代人の社会が、かれをそこまで追いつめてしまったのにほかならない。・・・かれは他人の自我意識にはもちろん、自分の自我意識にもたたかいを挑んでいるわけではなく、自我意識そのものの無意味さから出発している・・・芸術と生活との、現代的な関わりを暗示しておきたい・・・》
①その新しさゆえに理解してもらえぬ小田文学
②《でたらめの寄せ集めを性格と称し、これを聖化して自我と呼んでいる。》
③死の感覚に迫ることによって、《生のリアリティを把握》
④《小田仁二郎の作品はあくまで知性の文学》(ポルノグラフィーとして読んでは理解できない)
⑤「触手」は日本で初めての《完全な一人称小説》
⑥自我意識(他人あっての「自我意識」=常に評価にさらされる自分)以前の一人称世界
⑦《自意識(=他人の眼)の充満した近代人の社会が、かれをそこまで追いつめてしまった》
⑧文学(芸術)を通して自我意識の無意味さに気づき、その実感が生活にまで及ぶ。小田文学のもつそのインパクト性→《芸術と生活との、現代的な関わり》
-
現代的意義
○「常に新しいということは、過去も未来もないことの証明」( マドモアゼル・愛)https://www.youtube.com/watch?v=hEGfmgL8QSw
《海に打ち寄せる波は有史以来続いていても、同じ波は二度とありません。川の流れも、雲の形も同じです。似ているように見えても、同じものは絶対にない。 物事に繰り返しはなく、常に新しい波、新しい流れであり、人間も常に新しく存在しているので、生きていられるわけです。 日々いつも同じように見えますが、波や川の様相と同様、同じ日はなく、同じ自分はいなくて、常に新しい自分になっています。 変化の中にいるわけで、野球なども同じようなことをやっているように見えても、毎回違うわけです。存在しているものは、要するに常に新しくなっているので、存在できていることになります。 しかし、私たちの意識がそれを認めませんので、自分を固形物として捉えるようになっていきます。変わらないもの、変化しない自分として受け止めていたら、退屈になります。 常に新しいとは、過去にとらわれることも、未来を恐れる必要もないことを意味します。変化の中に身を置き、自分を変化体として捉える。そうすれば、何をしなくてはいけないとか、どうあらねばならないというかたくなさが消えていきます。 風の時代と言われますが、人間を固形物化や固形意識から解き放つことがテーマでもあるでしょう。 今年も残すところ2か月となりましたが、おそらくまだ波乱が予想されますし、来年もきっと驚きの連続でしょう。そうした流れの時もあるわけで、変化し、生きているからでもあります。 常に新しい変化や常に新しい自分であるとの立場に立てば、気が楽になるはずで、それでいいのではないかと思う次第です。真面目過ぎたため、私たちは知らないうちに固まってしまっていたように思います。 おびえてない子供は変化の中で生きているので、常に新しい感じがします。誰でもそうなれば楽しくなるのだと思います。しかしおびえた子供は変化が止まります。私たち大人は常におびえているので、あたらしく生きられないまま過去のことや未来のことで悩んでいます。》
(以下補遺分)
○ゼニカネ経済の終焉:「持ってナンボの経済」から「使ってナンボの経済」へ
・福田恆存:「人間は生産を通じてでなければ付合えない。消費は人を孤独に陥れる」。小林よしのり「福田恆存のこの言葉を噛みしめよ」(『修身論』)
↓↓↓
『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事 』からの解放
■「ブルシット・ジョブ」とは?
◇ブルシット・ジョブの最終的な実用的定義
ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている。(カネのためでしかない仕事)
◇ブルシット・ジョブの主要5類型
1. 取り巻き(flunkies):だれかを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせたりするためだけに存在している仕事
2. 脅し屋(goons):雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素をもち、そのことに意味が感じられない仕事
3. 尻ぬぐい(duct tapers):組織のなかの存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事
4. 書類穴埋め人(box tickers):組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事
5. タスクマスター(taskmasters):他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブをつくりだす仕事
○デカルト的感覚からの解放
川喜田二郎著『「野生の復興」デカルト的合理主義から全人的創造へ』(祥伝社 平成7年)の終章。(→https://oshosina.blog.ss-blog.jp/2006-03-23)・
《・・・・・管理社会の中で育った個人主義者は、他人を押しのけてでも自分が上に立ちたいという権力欲の虜になりがちである。親子・夫婦・友人たちとの、もともと持ち合わせた素直な人間らしさよりも、この権力欲を最優先する。そうして、それがもともとの偽らない人間性だと信じ込みたがる。・・・・・文明の毒気に当てられてもけっして崩れない、鍛えられて逞しい素朴人を、いかにして育て、保護するか・・・
・・・・・(自分にとって未知なひと仕事を、白覚的に達成することによって、人の心は)この世が瑞々しく見えてくる。青春が甦る。
馥郁たる香りがどこかから匂い、万物に愛と不思議を感ずる。利己心も利他心も、それぞれが大切な大自然からの授かりものと感ずる。どんなに状況が変わっても、その状況の中で主人公でいられる。しかも「私は山川草木のひとつである」という、言いしれぬ謙虚さを覚える。
自分のことを、ごく当たり前の人間だと感ずる。たとえば、死ぬことはひじょうに怖い。なぜなら、もともとそう怖れるようにこの世に送り出されたからである。ただ、死ぬのは怖くても、そのくせあまり生命に執着していない。
それはどうやら、自分が死んでも、私を包んでいた大きな伝統体は、まだまだ生き続けていてくれるからである。
なんと、これが安心立命というものに近いのかもしれない。
ただ、私が今ハッキリ言えることは、誰もがあのヘゲモニズム(常に他より上を目指してやまない覇権主義)の地獄から抜け出し、それぞれに安心立命を得た方がよいということである。
このような内面体験の一つの大きな特色は、もはや「自我」という固い観念の穀を内側から叩き破って、広い世界の自由で新鮮な空気を深々と呼吸していることなのである。
「自我」ではなく、知・情・意いずれをも備え、肉体そのものである「己れ」として生きている。
しかもその「己れ」は、そう自覚した方がよい場面でだけ存在するのであって、それが必要でなくなったら、いつでも「己れ」を退場させてしまう。つまり「己れ」は実体ではないのであって、方便として存在するだけなのである。
眠くなったら、「己れ」などなくなってしまう。仕事に打ち込んだら無我の境地になる。彼女に首ったけになったら、我を忘れる。何かの使命を感じたら、献身をも恐れない。こういったことは、誰でもよく知っているではないか。
ならば、それを正直に受け容れたほうがよいのではないか。
文明は不幸なことに、方便としてしか存在しない「自我」という観念を、何か固定した実体のように錯覚させてしまった。そうして、それによって、一方では「自我」の消滅におぴえつつ、他方では留まることをしらぬヘゲモニズムという奇形児を生んでしまったのではないか。》
○(デカルト的)知の極みから、知以前の「生きられた世界」へ。小田文学が描き出す宮内の情景から心によみがえるなんともいえない感覚こそ「生きていることそのもの」。
○《ヨーロッパ人は夜空を見上げて「わたし」というが、ロシア人は果てのないステップを見渡して「われわれ」という。・・・ロシア人はいまふたたび「われわれ」を謳っているが、この「われわれ」はユーラシアを意味している。》(ゲイリー・ラックマン『トランプ時代の魔術とオカルトパワー』2020)→アレクサンドル・ドゥーギン(1962-)の「新ユーラシアニズム」
(以上補遺分。以下削除分)
○プーチンの思想的背景としてのアレクサンドル・ドゥーギン(1962-)
(ドゥーギン:地政学的な見地から、ロシアを中心とした「新ユーラシア主義」を提唱し、米国や西欧を中心とした「大西洋主義」に対抗すべきだと主張。今年8月、娘が自動車爆破で暗殺される。)
《米国を中心とした自由主義の終焉に対し、ドゥーギンが提唱する政治理論が「第四の政治理論」である。この理論の基礎は、個人、人種、国家にはない。ドゥーギンが依拠するのは、ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーの哲学である。
これまでの主要な政治理論の主体として定められていたのは、自由主義では個人、共産主義では階級、ファシズムでは国家や人種だったが、第四の政治理論の主体はそのどれでもない、純粋な存在者である「ダーザイン」だという。一体どういうことだろうか?
ダーザインとは日本語で「現存在」と訳される。・・・ドゥーギンはこのダーザインを“純粋な存在者”であり、“本来的”だと指摘する一方、その反対に・・・「ダスマン」を対置している。ダスマンとは日本語で「世人」と訳されることが多く、誰とでも取替え可能で、”非本来的な“状態の人を指す。”生気のない人形“とドゥーギンは表現している。
さらに、ドゥーギンはハイデガーの哲学史観を要約し、古代ギリシア哲学から現代科学まで続くダーザインとダスマンの関係を語る。それによると、古代ギリシア人の哲学的焦点となった“存在”の問いは、純粋存在(存在すること)と存在の表現様態(存在するもの)を混同するようになってしまい、純粋存在が忘却されてしまったという。・・・プラトンは純粋存在を忘れ、真理を人と存在するものの間に置くことで、真理の探究を存在の問いではなく、知識の問題にすり替えてしまった。そして、計算可能な「存在するモノ」の方が優位となったため、それが“計量的思考”を生み出し、科学技術の進歩を招いたという。・・・純粋存在を問うていたダーザインとしての人間が、プラトン哲学、そしてそれに続く科学技術の進歩により計量的思考、交換可能なモノのことしか考えず、自分自身もそのようなモノとして扱われるダスマンに堕してしまったと考えているようだ。・・・
計算可能なモノを取り扱う計量的思考は、人間を労働者としてモノ化してしまう資本主義を生み出した。そして、資本主義が生まれる土壌を提供したのが、個人主義、私的所有権、自由市場の基礎となった自由主義である。》(「アレクサンドル・ドゥーギン完全解説!
」https://www.excite.co.jp/news/article/Tocana_201805_post_16969/)
(以上削除分)
6.むすび
○《わからないとは何であるか。わかろうとしないことである。精神の怠惰にすぎないのではないか。》(『文壇第二軍』)まだまだ小田文学から汲み取るべきことは多い。
○自我至上の生き方うたがひ街を歩く生あたたかき風の吹く夕べ 小田たか




コメント 0